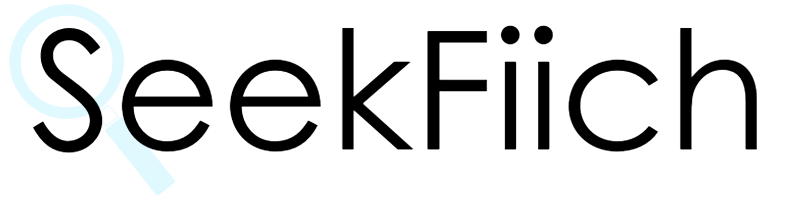前章で紹介したように、シークフィーチでは以下2つの条件を満たす選択を「自分に合う選択」と考えています。
- 自分の「才能」「性格」「目標」「希望」「夢」「傾向」など、先天的・後天的問わず、自分がもつ何らかの要素に合う
- その選択によって「充実感」と「納得感」の両方を得られる
なぜ2つの条件を満たす必要があるのか?今回は、シークフィーチが「自分に合う選択」の条件は2つあると考える理由についてお話します。
「自分がもつ何らかの要素に合う」は大前提となる要素
1つ目の「先天的・後天的問わず、自分がもつ何らかの要素に合う」は大前提といえる条件です。
そもそも、先天的な才能や素質、後天的な願い、希望、目標、興味、いずれにも合わないものは選択肢になり得ないでしょう。明記するまでもなく、「自分に合う選択」の絶対的な条件といえます。
何を基準にするかによって合う・合わないの判断が変わる
「自分がもつ何らかの要素に合う」という条件だけで自分に合う選択かの判断はできません。どの要素を基準とするかによって、合う・合わないの判断が変わるためです。
例えば、好きなものと才能があるもの、どちらがその人に合う選択だと思いますか?
この答えは人によって異なるでしょう。どの要素を基準とするべきかについて、絶対的な答えはないためです。
「好きなものこそその人に合う選択肢」と考えれば、「好きだけど才能はない」「好きだけど自分の成し遂げたい目的とは方向性が違う」「好きだけど何となく続かない」といった選択肢は、いずれも「好き」という条件を満たしているという理由だけで、その人に合う選択肢となります。
しかし、本当にそうでしょうか? きっと、そうではないと思った人が多いでしょう。
才能が発揮できる分野ではないけれど、好きで熱意をもって取り組めるなら「合う選択」といっても良いはずです。人より上手く出来ず悔しい思いをすることばかりな分野でも、「それでもやりたい」「好きな気持ちは変わらない」「強く惹かれる」と思うのであれば、魂が求める選択といえるし、その選択を本当の意味で嫌だとは思わないはずです。長く続くし熱意をもって取り組めるため、いずれ大きな成果が出ると期待できます。
一方で「好きだけど才能がないから辛い。熱意が続かない」と感じる場合、その人の魂は、好きな分野よりも才能がある分野を求めていると考えられます。その人にとって、好きだけど才能がない分野は「合わない選択」といえるでしょう。
「特に努力しなくてもそれなりの結果は出せる。けれど好きだとは思えないし熱意もないから続けたいと思えない」といった分野もあります。先ほどの例とは反対で、才能はあるけれど好きではない分野です。
「才能」を基準にすれば、間違いなくその人に合う選択です。しかし、「好み」の観点では合いません。熱意がもてない点から、「興味」の観点でも合わないと考えられます。
一方で「好きだとは思えないけれど、才能を発揮できる分野だから、これを極めることが自分の使命だと感じる」と心から思えるのであれば、好きという面では合わなくても、その人に合う選択といえるでしょう。
このように「好き」と「才能」という2つの要素だけでも、どちらに着目するかによって合う・合わないの判断結果は全く異なるものになる可能性があります。特定の要素に合うか否かだけで、その人自身に合う・合わないか一概には言い切れないのです。
そもそも、その人がもつあらゆる要素に合う選択肢は基本的には存在しません。才能はあるけれど好きじゃない、好きだけど才能がない等はよくあることです。
だからこそ、「その人のもつ何らかの要素に合う」は絶対的な条件ではあるものの、それだけで、その人に合う選択肢か否かを判断することはできません。
充実感や納得感を得られる選択肢こそ、本当に合う選択肢
改めて、シークフィーチが考える「自分に合う選択」の2つの条件を紹介します。
- 自分の「才能」「性格」「目標」「希望」「夢」「傾向」など、先天的・後天的問わず、自分がもつ何らかの要素に合う
- その選択によって「充実感」と「納得感」の両方を得られる
これまでにお話したように、1は大前提といえる条件です。何の要素にも合わなければそもそも選択肢になり得ないため、あえて条件として指定する必要はないかもしれません。
だからこそ、特に大切なのは2の条件だと考えます。1の条件を満たす選択肢の中から、自分が充実感や納得感を得られるものを選ぶことが大切です。
とはいえ、選択肢を選ぶ前の段階で「どの選択なら、自分が充実感や納得感を得られるか」を判断するのは難しい……というか不可能でしょう。そのため、まずは1を満たす選択肢の中から自分に合いそうなものを直感で選び、選んだ選択肢に対して充実感や納得感をもてるかを意識するのがおすすめです。
「充実感や納得感をもつことを意識する」については次の記事で解説します。
まとめ
- 何を基準にするかによって合う・合わないの考え方が全く異なるものになる以上、特定の要素に合うか否かだけで、その人自身に合う・合わないか一概には言い切れない
- 「自分がもつ何らかの要素に合う」という条件を満たす選択肢の中から、自分が充実感や納得感を得られるものを選ぶことが大切
- 選択肢を選ぶ前の段階で「どの選択なら、自分が充実感や納得感を得られるか」を判断するのは難しいため、まずは直感で選ぶのが良い
次の記事はこちら 5.合うものは自然と続く
前の記事はこちら 3.選択は「正しい・正しくない」ではなく、「合う・合わない」で考えるべき